今回のテーマは『肺炎の看護計画』です。事前・事後学習にそのまま活かせるように根拠付きでまとめました。
また、看護実習での看護計画立案時にも役立てて下さい。
では、いきましょう!!『肺炎の看護計画』!!
#1 気道に痰が貯留し、換気が障害されている
OP 経過観察項目
・呼吸状態
・痰の性状、痰の貯留の状態・有無 根拠:援助効果の評価に有用であるため
痰の貯留部位(症状、肺音の聴取、炎症所見のデータの活用する) 根拠:貯留部位が確認できれば効果的に介入・評価できるため
・喀痰、咳嗽、呼吸に影響する因子(症状、生活活動、環境)
・食事、水分摂取状況、脱水症状の有無
・効果的な痰の喀出に必要な患者の知識や行動
TP 看護項目
・気道の保湿(湿度調整、水分摂取、含嗽、口腔ケア、医師の指示による吸入)により、粘稠度を低くして、痰の喀出を促す 根拠:湿度、重力、徒手的な加圧、呼吸法、催咳法(気流速度・量の変化)など、原理の違う方法を組み合わせることで、相乗的効果が期待でき、侵襲が少ない
・体位ドレナージ(重力を利用する方法)無理な体位は避ける 根拠:酸素消費量の増大、換気血流比の変化、不良な血管運動反射などで、低酸素血症や血圧低下を招く危険があるため→排痰体位(痰貯留部が肺全体で最も高く、区域気管支が垂直になる体位)を介助し、喀痰を促す
・スクイージング(スクイージングでは、患者の表情などを確認しながら加圧の程度に注意する) 根拠:基礎疾患によっては、出血や骨折などの危険があるため
・効果的な呼吸法、咳嗽を促すことにより、喀痰を促す(痰の喀出を促す介入は食事や排泄時間を考慮する) 根拠:食後や便秘は、横隔膜運動が抑制され、特に食後は嘔吐や誤嚥の危険がある
・腹式深呼吸(腹式深呼吸のデメリットに注意する) 根拠:気管攣縮の原因となったり、疲労感や呼吸困難を増強させることもある
・患者が行える生活行動を段階的に促す 根拠:生活行動を促すことで、痰の中枢気道への移動を促すだけでなく、呼吸筋などを利用することで、下側肺障害の予防となる。呼吸法、咳嗽法など効果的に行うため、身体的準備状態を整えることにもなる。また、意識的な運動と比較して「しなくてはいけない」という負担感が少なく、生活活動が抑制されているというストレスも軽減されるため
・喀痰吸引の実施(正しいカテーテルの選択、吸引圧、時間のもと実施) 根拠:粘膜損傷や低酸素血症を招く危険があるため
EP 指導項目
・咳嗽、喀痰の必要性を確認・指導する 根拠:患者とともに成果を評価できる
・咳嗽、喀痰の影響因子について確認する
・効果的な喀痰方法が実施できるように説明する
・痰の採取、吸引、吸入など検査、治療や医療的処置の目的、効果的な方法やそれに伴う侵襲を説明する
・禁煙指導 根拠:喫煙は気道粘膜を刺激し痰を増加するため
#2 身体症状に伴い苦痛が生じている
OP 観察項目
・症状の出現状況、程度(生活活動の抑制状況と関連させ観察する)根拠:苦痛の理解には、QOLの考慮が必要 、変化、経過、影響因子
・生活活動の状況(睡眠や休息障害、食欲低下、活動意欲の低下)、生活活動が抑制されている意識や思い
・苦痛の表現や表出の状態 根拠:苦痛の表現は個別性が高い
・症状や治療に関する認識、疾患の経過に関する思い 根拠:安楽な生活が送れるように支援することが重要なため
TP 看護項目
・原因となる症状を緩和する
咳嗽:気道刺激になる環境の調整(温度、湿度、清浄)
呼吸困難:呼吸運動を抑制する要因を調整(衣類、便通、食事の調整)、腹式深呼吸、口すぼめ呼吸の支援
胸痛:温罨法、精神的ケア、咳嗽法
発熱:体温調整を促す(室内環境、保湿)、発熱の軽減(冷罨法)、発汗時の保清、水分摂取
倦怠感:ベッド周囲の環境調整
・睡眠、休息がとれる環境の調整 根拠:肺炎は症状によってエネルギー消耗が苦痛につながり、不眠は苦痛を増強させるため、十分な睡眠をとることがエネルギーの回復につながる
・障害されている生活活動の支援 根拠:患者ができる行動に参加してもらうことで、生活活動抑制による苦痛の軽減につながる
・コミュニケーション環境の調整(訪室の回数)
・服薬(鎮咳薬、鎮痛薬、解熱薬、睡眠薬)の必要性について、患者、医師と相談する 根拠:薬物を用いることは、苦痛緩和のため必要であるが、発熱や咳嗽は防御反応の1つであることを考慮する必要がある
EP 指導項目
・苦痛を我慢しないで相談できるように話し合う 根拠:苦痛は主観的な側面が大きいため、周囲に理解されにくく、諦めや我慢につながることがある。苦痛の我慢は、病状の悪化や精神的な問題を発生させる。
・考えられる苦痛の予防方法を指導する
・効果的な症状の緩和方法を指導する
・睡眠や吸息が阻害されている原因について話合い、解決策を相談する
・リラクゼーション法について相談する
#3 食欲不振やエネルギー消費増加により栄養状態が不良となり、感染防御機能が低下している
OP 観察項目
・食欲、食事摂取状、量、食事摂取の影響因子
・栄養状態(アルブミン値、体重、脱水) 根拠:栄養状態低下の指標として血液中のアルブミン値が有用であり、アルブミン低下は、免疫学的防御機能を低下させる
・エネルギー消耗因子(高熱の持続、頑固な咳)
・生活活動状況
TP 看護項目
・食欲を増進する環境の調整
・食事中・食後の姿勢(2時間程度の起坐位)を支援する 根拠:食事による横隔膜の挙上は呼吸困難の原因となるため
・口腔ケア
・食事内容・量の調整、嗜好の考慮 根拠:横隔膜の挙上時間を短くするとともに、消化による代謝の効率をよくする
・食欲不振の苦痛症状の緩和、睡眠・休息のできる環境調整
・経口摂取が困難な場合、輸液管理
EP 指導項目
・体力の回復、感染防御能と関係づけ、無理の無い食事摂取の必要性を説明する 根拠:回復促進のため、無理をして摂取することでストレスになる危険がある
・嗜好を取り入れた捕食について相談する
#4 口腔内の乾燥や衛生状況が不良となり、粘膜障害が起こりやすい
OP 観察項目
・呼吸器症状の観察 根拠:口呼吸、発熱による脱水などは口腔内を乾燥させ、自浄作用は低下する。
・口腔内の衛生状況(乾燥、食物残渣、喀痰)、不快感
・清潔ケアの実施状況(歯磨き、義歯洗浄、含嗽)の有無
・水分摂取状況
・発熱、呼吸器症状(口呼吸、喀痰)
TP 看護項目
・水分摂取、含嗽を促し、口腔内の保湿環境を整える
・経口食が困難な場合は、積極的にケアを促す 根拠:口腔内が乾燥しやすい、食事を摂取しないことで、保清意欲が低下するリスクがあるため
・口腔内の清潔の促し、セルフケアの程度に応じて支援(毎食後、就寝前の歯磨き、義歯の洗浄、食物残渣や痰の除去) 根拠:食物によっては衛生状態が低下する。食後の含嗽は肺炎予防のうえでも効果的である
・絶食栄養状態の改善
EP 指導項目
・感染予防と関連づけて、口腔ケアの必要性の説明
・口腔ケアの方法の説明
#5 病状が悪化するかもしれないという不安がある
OP 観察項目
・発熱、呼吸状態(呼吸状態の増強)、胸痛など精神的影響の大きい身体症状、程度、変化、経過 根拠:呼吸困難は不安によって生じることがある
・生活活動の状況(睡眠や休息障害、食欲低下、活動意欲の低下)、生活活動が抑制されている認識や思い
・不安の表現や表出の状態(非言語的で態度や表情で表される内容) 根拠:不安の表現は個別性が高い
・症状や治療に関する認識、疾患の経過に関する思い
TP 看護項目
・原因となる症状を緩和する
・睡眠、休息がとれる環境の調整
・障害されている生活活動の支援(日常生活の援助では、意志決定を求めず、感情に寄り添う) 根拠:考えが集中しないときの意思決定は難しいく、提案を受け入れられない場合は、感情に寄り添うことが必要
・コミュニケーション環境の調整(訪室のタイミング、別室での面談) 根拠:不安について関心を持っていることを、非言語的に伝えることで、表出いやすくなる
EP 指導項目
・現在の生活目標について話し合う
・生活に対する欲求やそれが満たされない状況を具体的に聞く 根拠:はっきりしない不安の原因に患者自身が気づくきっかけを作ることが重要
・睡眠や休息が阻害されている原因について話し合う
・不安の原因になっている状況をコントロールする学習の機会を作る
#6 ガス交換障害が起こる危険性がある
OP 観察項目
・危険因子に関連する内容
・低酸素血症の発生の有無、程度、要因(Spo₂、チアノーゼ、呼吸困難)
・生活活動状況(活動内容、量、時間、頻度、行動様式)、休息のバランス、活動意欲 根拠:廃用症候群、下側肺障害、沈下性肺炎の予防
TP 看護項目
・呼吸困難の緩和
・気道の保湿(湿度調整、水分摂取、含嗽、口腔ケア、医師の指示による吸入)により、粘稠度を低くして、痰の喀出を促す
・酸素療法の看護(酸素療法中はCO₂ナルコーシスの発症に注意する) 根拠:慢性肺疾患の既往がある場合、発症しやすい 👉CO₂ナルコーシスについてはこちら
・安静療法の看護
・障害されている生活活動の支援
EP 指導項目
・呼吸困難時の呼吸法を指導する
・低酸素血症の改善に口すぼめ呼吸の指導 根拠:口をすぼめて、ゆっくりとした呼気をすることで、呼気の初期流速の減速、気道内圧上昇による気道閉塞防止、呼気時間の延長による呼吸数の減少、換気量の増加ができる
・酸素使用時の注意を指導する
今回は、「肺炎の看護計画」についてまとめました。
看護実習では、肺炎は必ずといって良いほど出会う疾患です。
ぜひ、この記事を活かして下さい。
では、また!!

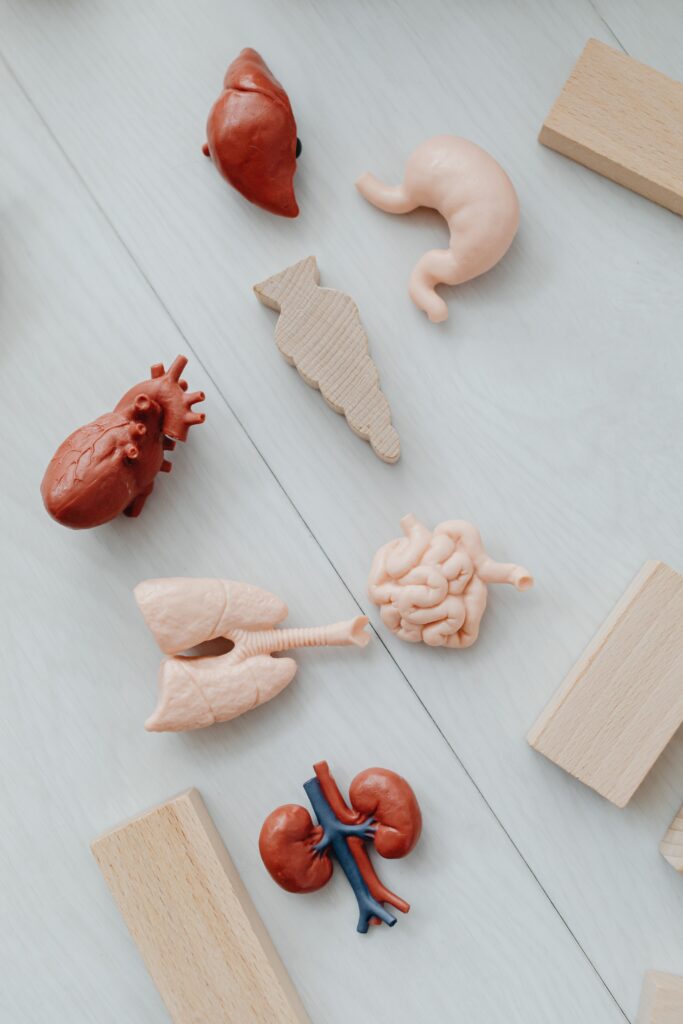

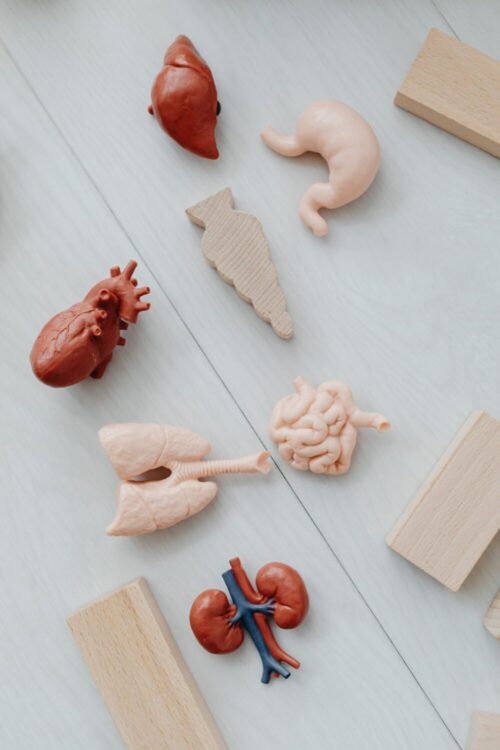
コメント