こんにちは。現役看護師の無理やあブログ管理者の無理やあです。
この無理やあブログは、記事をそのまま書けば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。
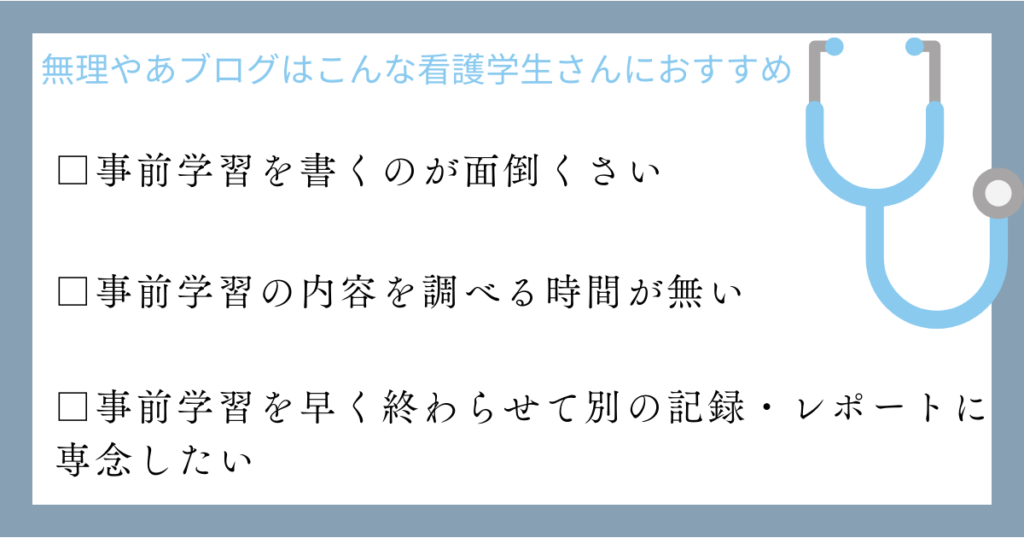
校内演習でも事前学習・・看護実習でも事前学習・・何かと色々レポート提出・・時間が無い看護学生さん、この無理やあブログを活用して少しでも時間を獲得して下さい!!
今回のテーマは『呼吸器疾患の基本』。
私も、現役時代苦手でした。。。CO₂ナルコーシスとか。。
なので、頑張ってまとめます!!では、いきましょう『呼吸器疾患の基本』!!
※あわせて読んで! 『肺炎について』下の画像をクリック👇
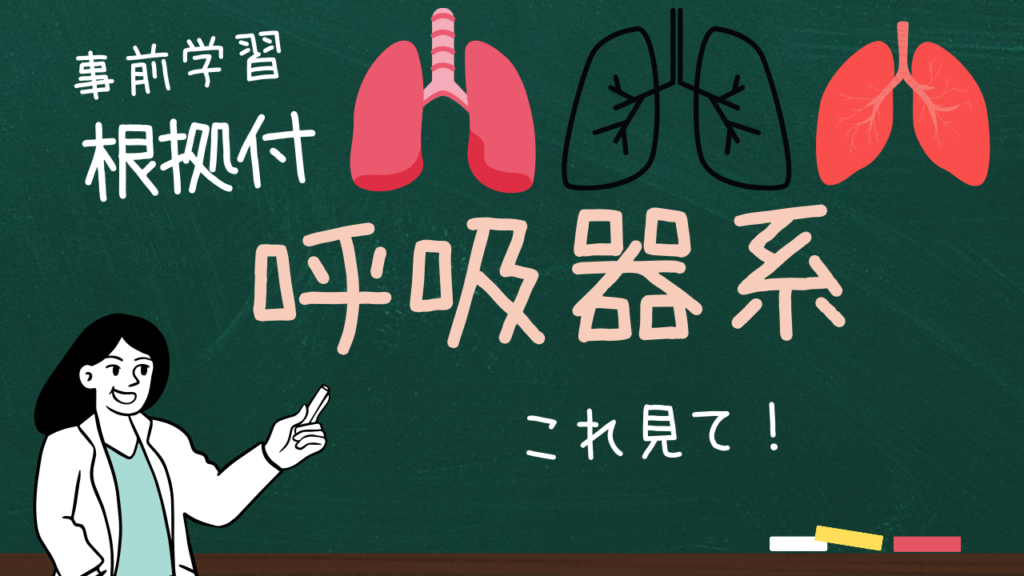
肺の構造
・肺は左右に1つずつある
・肺には、斜裂(大葉間裂)、水平裂(小葉間裂)という切れ目が入っている
・右肺は上葉・中葉・下葉に分かれる。
・左肺は上葉・下葉に分かれている
・右肺がS¹~S¹⁰の10区域、左肺がS¹⁺²~S¹⁰の8区域の肺区域に分けられる
呼吸の仕組み
・肺胞中にはO₂が多く、血管中にはCO₂が多いため、拡散の原理により濃い方から薄い方へ移動する
・血液は肺胞を通ることで、空気中の酸素をたっぷり取り入れ、二酸化炭素を空気中に排出している。これをガス交換という。
外呼吸
・赤血球中のヘモグロビンが酸素と結びつくこと、また血中の二酸化炭素が空気中に出ていくこと、つまり肺で行われている血液と空気との間のガス交換を外呼吸という
内呼吸
・細胞がヘモグロビンから酸素を受け取り、二酸化炭素を血液中に送り出すこと、つまり末梢組織で行われる血液と細胞との間のガス交換を内呼吸という
呼吸運動
・呼吸は、入眠中も止まることはない 根拠:延髄を中心とする呼吸中枢と橋の呼吸調節中枢等により、不随意に呼吸運動が維持されているため
・成人の呼吸数は1分間あたり約16~18回で、1日あたり約2万回にもなる
・脊髄損傷や神経疾患等が原因で、人工呼吸器が必要になる 根拠:呼吸中枢から呼吸筋への指令のルートが障害されると、呼吸ができなくなるため
・外界の空気を肺に取り込む(吸息運動)排出させるのを(呼息運動)という
・肺は膨らんだり縮んだりしているが、肺そのものに肺を動かす骨格筋は存在しない。呼吸には、肺の周囲にある呼吸筋(横隔膜、内・外肋間筋、胸鎖乳突筋、腹斜筋等、呼吸に関わる筋肉の総称)が重要な役割を担っている
吸息運動と呼息運動
①吸息運動とは、外肋間筋が収縮することにより肋骨と肋骨の間が広がり、横隔膜も収縮し、下がることを言う。
②呼息運動とは、吸息運動により空気が引っ張られ、気道を通って肺の中に入っていき、肺が膨らむ。膨らんだ肺は、その弾力により自然に収縮する。これに伴い横隔膜は上がり、肺の中の空気は再び気道を通って大気中に排出されることを言う。
・①と②が呼吸の1サイクルで、成人の1回換気量は500ml程度である
・呼息運動が終わっても肺はぺちゃんこにはならない 根拠:肺は胸壁内膜を覆う壁側胸膜と肺を包む臓側胸膜(肺胸膜)という2つの膜で覆われており、両膜の間(胸膜腔)は吸気時・呼気時ともに大気圧よりも陰圧がたもたれているため、肺は引っ張られる形で膨張し、その形態を維持している
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
・COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、たばこを主とする有害物質を長期に吸入することで生じる炎症性の疾患で、通常は進行性の経過をたどる
・スパイロメトリーで1秒率<70%を満たし、他の気流制限をきたし得る疾患が除外されたとき、COPDと診断される
・COPDは慢性気管支炎と肺気腫病変が様々に混在し、両病態によって気流閉塞をきたした症例に対する病名として生まれた概念である
・慢性気管支炎は咳・痰などの症状が年に3か月以上あり、それが2年以上連続して認められるもので、症状が他の肺疾患や心疾患に起因しないものを言い、冬季に悪化するのが一般的
・肺気腫は肺胞が慢性的な炎症のために破れ、くっつきあい、嚢胞(ブラ)になった状態。肺が膨張し気道をつぶし、呼吸が困難になる。一度壊れた肺胞は元には戻らない。
・肺気腫は、肺が過膨張する 根拠:肺気腫は肺胞壁が壊れて、肺が膨らみやすくなった状態のため
・慢性気管支炎では、慢性の気管支炎症で気道分泌が亢進している。また、気管支壁が肥厚し気管支が狭くなっていることが特徴
・慢性気管支炎も肺気腫も中年男性に多く、多くの場合、両疾患を合併している
・COPDは徐々に生じる労作時の呼吸困難や慢性の咳、痰を特徴としているがこれらの症状に乏しいこともあり、自覚症状が出る頃には重症化していることも多い
・COPDは別名たばこ病という異名があり、喫煙と密接に関係しており、COPD患者の90%に喫煙歴がある。喫煙開始年齢が若いほど、COPDに罹患しやすい
COPDのリスクファクター
・喫煙、大気汚染、受動喫煙、粉じん、有害化学物質の吸入
喫煙指数(ブリンクマン指数) (国試)
・ブリンクマン指数は喫煙習慣の指標
・1日の喫煙本数×喫煙年数で表される
・ブリンクマン指数が400以上になると肺がんのリスクが上昇し、700以上になるとCOPDなどの呼吸器疾患や狭心症などの心疾患に罹患しやすくなり、喉頭がんや肺がんのリスクが高くなる
COPDの画像検査
・COPDの画像検査は胸部エックス線とCTの実施
・胸部エックス線写真は、慢性気管支炎や肺気腫の状態、肺炎や気胸が起きていないか確認するために重要
エックス線画像
・肺気腫では、画像は「黒く」見える 根拠:肺に空気が溜まることで肺野の透過性が上がるため(肺が膨らみ空気が多く入るため、エックス線は肺を通り抜けやすくなるため) ちなみに、肺紋理(肺野末端に見える気管支や血管による線状陰影)も減弱する
・横隔膜は形は平坦になる 根拠:肺に押し下げらるため
・横隔膜は低い位置になる
・壊れた肺胞が融合したできた「嚢胞(ブラ)」(上肺野によくみられる)も黒く見える
・心臓の形は「しずく」かたちに見えるため、滴状心と呼ばれる 根拠:肺に過剰に溜まった空気により心臓がおされ大動脈以下の心臓がほっそり滴💧のように見えるため
CT検査
・肺気腫であれば、低吸収領域が散在している
※あわせて読んで 『肺がん』について下の画像をクリック👇

スパイロメトリー
・スパイロメトリーという検査では肺活量が測定できる(国試)
・スパイロメトリーを使いスパイログラム(肺気量分画)というグラフが得られる
・肺気量分画測定はゆっくり実施することが重要 根拠:速いと胸腔内圧上昇で気道が圧迫され、虚脱が起こり、肺胞に空気が残存するair trappingが生じることがあるため
肺活量とは
・肺活量とは1回換気量+予備吸気量+予備呼気量 「最大限息を吸った状態から、最大限息を吐いたときに、吐き出すことのできる空気の量」 (国試)
・ふつうに吸ったり吐いたりする空気の量が1回換気量で、ふつうに息を吸った状態から、さらに頑張って息を吸ったときの「いつもより余分に吸える空気の量」が予備吸気量になる
・ふつうに息を吐いたときから、さらに頑張って吐くことのできる空気の量が予備呼気量
・残気量に肺活量を足すと、肺の最大容量を求めることができる。これが全肺気量。
・COPDでは残気量が多くなる 根拠:COPDでは肺胞が破壊されて収縮しなくなってしまい、吸うことができても吐き出せなくなってしまい、肺の中に空気が残ってしまうため
・COPDでは吸気と同じ量の呼気を吐き出せないため、残気量が増え、肺が過膨張を起こす
換気障害
・換気障害には、閉塞性換気障害と拘束性換気障害の2種類がある
・COPDや気管支喘息などの閉塞性換気障害では、気道が狭くなって息を「吐く」ことが困難になるという特徴がある
・拘束性換気障害の代表は肺繊維症や間質性肺炎であり、肺が硬くなり膨らみにくくなり「吸う」ことが困難になる
・閉塞性換気障害では1秒率が低下する(<70%)(国試)
・拘束性換気障害では肺活量が減少する(<80%)(国試)
フローボリューム曲線はスパイロメーターを用いて得られるグラフ
・検査方法は、普段の呼吸を何度か繰り返してから、思いきり息を吸い、できるだけ早く一気に吐き出す。これを3回程度実施し、一番良い結果のもので判定する。被験者の努力性に大きく依存する(努力性呼出)検査である。
・COPDの患者のフローボリューム曲線では、曲線のくだりの部分がへこむのが特徴的な形となる(国試)
・COPDでは1秒率が低いほど予後不良であるといわれている
ガス分析
・動脈穿刺によって動脈血を採血する検査
・ガス分析は「血液に酸素を取り込み二酸化炭素を捨てる」ガス交換機能を調べる
・ガス交換機能は肺胞と毛細血管の間の壁がどのくらいガスを通すかによる
・ガス分析は動脈血酸素分圧(PaPO₂)や動脈血二酸化炭素分圧(PaCO₂)を測定することが多い
基準値
・PaPO₂ 80~100Torr(mmHg)
・PaCO₂ 35~45Torr(mmHg)
呼吸性アシドーシス
・COPDの患者はPaO₂は低下してPaCO₂は上昇する。(国試)つまり、血液中にCO₂が溜まることで血液が酸性化する呼吸性アシドーシスになりやすい。根拠:息を吸うことはできるが吐き出すことが出来ないことで、新しい酸素を取り込むことが困難となり、酸素不足になる、そして二酸化炭素が増えるため
・60TorrよりPaO₂が減った状態を呼吸不全という
パルスオキシメーター
・動脈血の酸素不足を早期発見できる (国試)
・メリット:測定には、指の表在動脈を使用しているため、非侵襲的かつ連続的に酸素飽和度を測定できる
・デメリット:手指が冷たいなどで、指先の血行不良:末梢循環不全やうっ血があると脈とが弱くなるため正確な測定ができない
・マニキュアや強い光が当たっている場合、動脈的ヘモグロビン酸素飽和度(SaO₂)から値がずれることがあるため注意が必要
・SpO₂=経皮的動脈血酸素飽和度(サチュレーション)を測定できる
・SpO₂≒SaO₂である
・正常値:95~100%
・光で測定できる 根拠:酸素と結合しているヘモグロビンと結合していないヘモグロビンは、吸収する光の波長が違う。パルスオキシメーターはこの2種類の波長の光をつくり、指などの組織へ光を当て、吸収されずに通り抜けた光を測定する。それぞれの波長の光の量を計算することで、2種類のヘモグロビンの量を測定したことになる。これで測定できる。
パルスオキシメーター装着時の看護
・受光部と発光部が平行になるように装着する
・マニキュアや汚れは落とす
・指先の血流を良くしてから測定する
・パルスオキシメーターを継続して装着する場合は、定期的に測定する指を変える必要がある 根拠:センサーの光によって皮膚障害を起こす怖れがあるため
・SpO₂=90%のとき、PaO₂=60Torrであり。PaO₂≦60Torr=呼吸不全であることから、PaO₂が60Torrより低いとSpO₂が急激に低下しやすい危険な状態である (国試)
CO₂ナルコーシス
・通常体内に「酸素が足りないとき」あるいは「二酸化炭素が多すぎるとき」に「呼吸しようと」スイッチが入る
・酸素の減少を感知する受容体は頸動脈小体にある
・二酸化炭素の上昇を感知する受容体は延髄にあり、それらのスイッチによる信号は橋~延髄にある呼吸中枢に送られる
・COPDでは慢性的に体内に二酸化炭素が多すぎる状態なため、やがて延髄のスイッチが反応しなくなり、二酸化炭素が多すぎても「呼吸をしよう」という信号が出なくなってしまう。つまり、COPDの患者では「呼吸しよう」というスイッチが入るのは「酸素が足りないとき」だけになる。
👇
・この状態で高濃度酸素を吸収し、血中へ十分に酸素が満たされると、本当は「二酸化炭素が多すぎる」状態になっていても、「呼吸をしよう」とするスイッチが入らなくなってしまう。増加した二酸化炭素が呼吸中枢を抑制することによって起こるのがCO₂ナルコーシスである。
CO₂ナルコーシス時の看護
・人工呼吸器で強制的に呼吸をさせ、二酸化炭素を血液から追い出す
・人工呼吸器は、肺換気量の低下や低酸素血症の他、努力呼吸がみられたり、呼吸数<5回/分または>40回/分など、呼吸仕事量の軽減が必要とされる場合に使用する
呼吸障害の患者が楽になる体位・呼吸方
・ベッドをギャッジアップし、ファウラー位にする 根拠:ファウラー位であれば、内臓が重力で下がり横隔膜が運動しやすくなるため
・口すぼめ呼吸 根拠:口をすぼめてゆっくりと少しずつ息を吐くことで、気道内圧が高まり気道が広がり、息を吐きやすくなるため
息を吸うことよりも吐くことがポイントとなる
・腹式呼吸も有効
最後に
今回の呼吸器の基本、本当に本当に簡単にしてみました。
是非、活かして下さい。
では、また!!

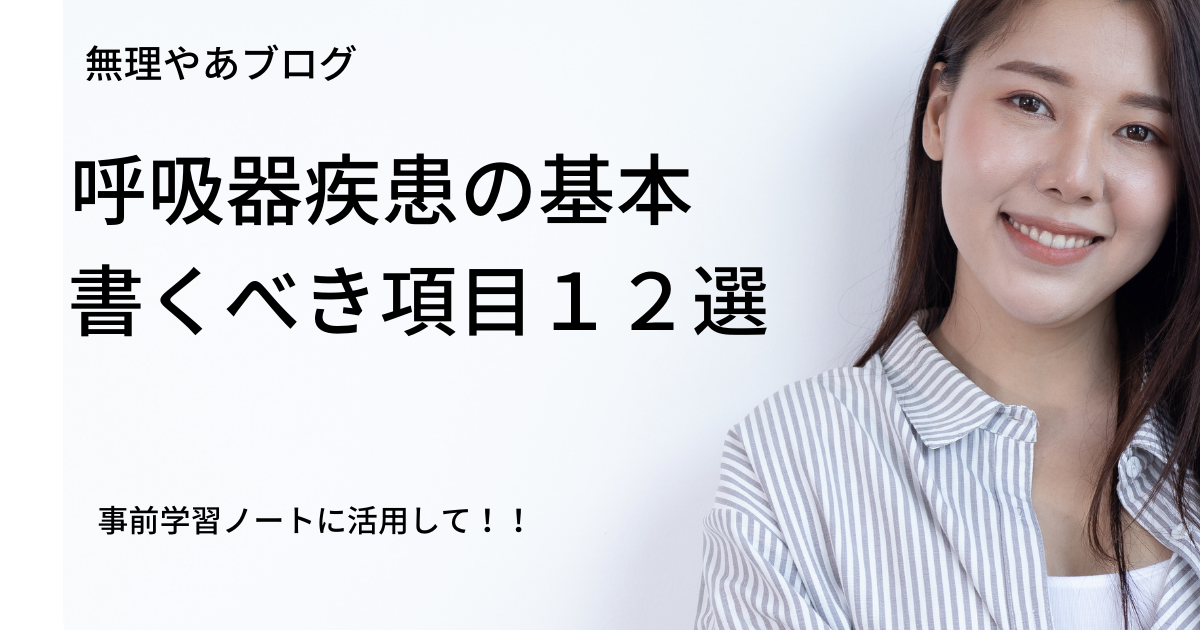










コメント